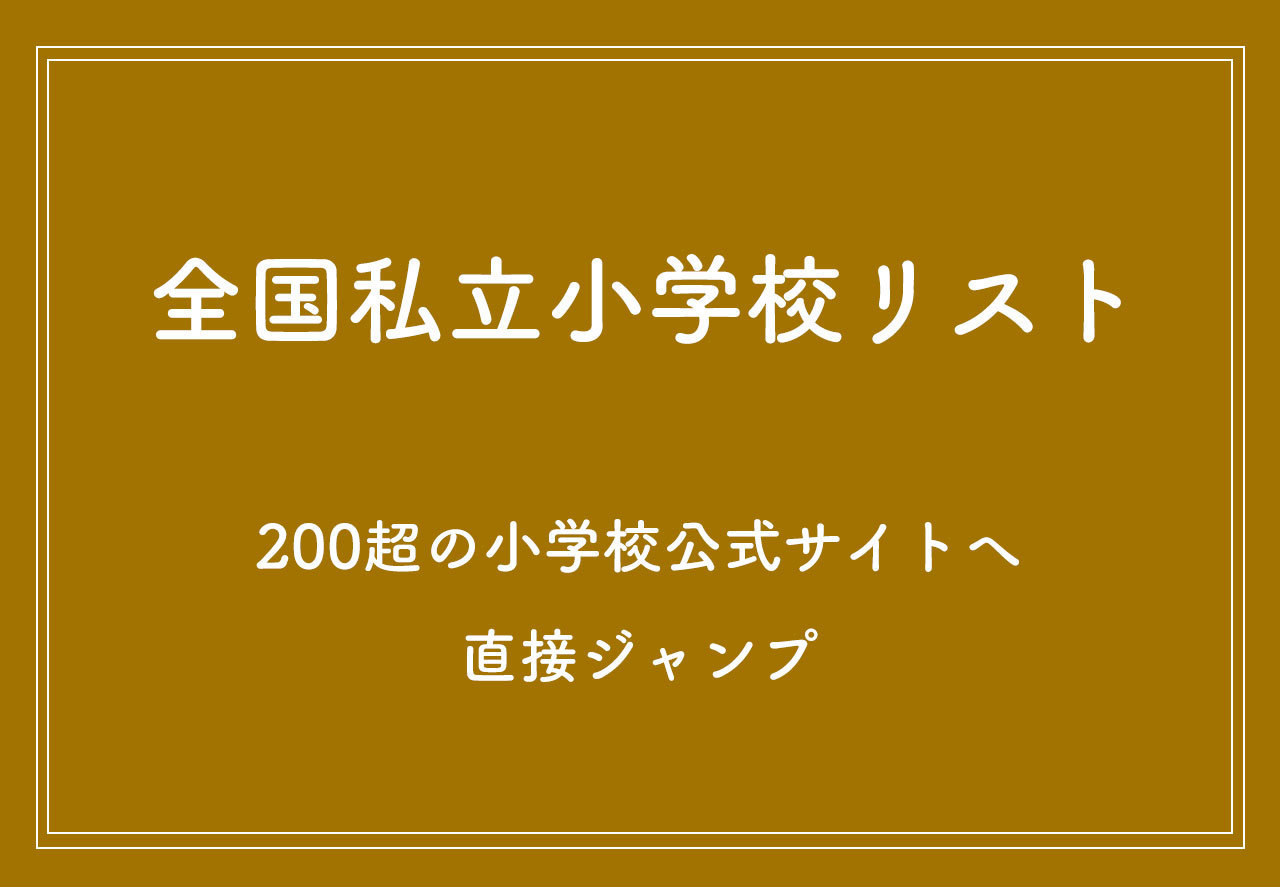相模女子大学小学部

スクールコンセプト
毎日会いたい友達がいる 毎日受けたい授業がある
自分からできる子
〒252-0383 神奈川県相模原市南区文京 2-1-1
TEL : 042-742-1444
http://www.www.sagami-wu.ac.jp/sho/
最寄駅●相模大野駅(小田急線)北口より徒歩10分
おもしろい! やってみたい、つくりたい 柔軟な発想から探究を進める学びがこれからの時代を生き抜く力となる
探究学習、使える英語、コミュニケーション力を重視し、進化を続けるAI技術の基礎を身に付けるAIリテラシーとは。

プログラミング

川原田康文校長
AIリテラシーの育成
小学部がプログラミング教育を導入して7年目を迎えた。専門家として招かれた川原田康文先生が「STREAM(ストリーム)」〈※1〉を主唱して始まった、ロボットを使うプログラミングの授業はすっかり定着している。
川原田先生は、現在は校長として小学部を束ねる立場にある一方で、研究者として「AIリテラシーの育成」をテーマに大学と共同研究を進めている。
AI〈※2〉は人工知能ということなので、IT〈※3〉の理解も活用もこれから学習する小学生には先の先のことのように思えるのだが、研究は小・中・高・大それぞれの段階での育成がテーマということだ。
「リテラシーは使いこなす技能を意味するのみではなく、AIをどう活用するか、使うとどういうメリットがあるかを理解することであり、進化とともに新たなリテラシーが生まれることもあります。AIをつくる側になる人は少数ですが、活用する人はほとんどすべての人ですから、AIリテラシーはこれからの時代に生きる上で欠かせません」。
現在小学部で使用しているロボット教材には、付いているセンサーが一秒間に何十個というデータを集める。そのデータ量が大きいとコッチへ動け、小さいとアッチへ動けとロボットに指示する。しかし、「この膨大なデータはどこから集まって来たのだろう」「どう活用できるのだろう」と疑問をもったなら、その疑問を要素に集めたデータを表にしたりグラフにしたりすることもできる。
「小学部のプログラミングテキストにはそこまで入れてあります。研究していて気がついたのですが、この、知りたいことの答になるかもしれない情報を取り出すことがAIリテラシーの育成、第一歩なのです。化学の実験のように目の前で装置が反応するわけではなく、おもちゃ感覚でロボットを動かし、データはタブレットの隅に出て来るので、子どもたちに学習している感じはないかもしれませんが」と笑いながら川原田先生は、小学校では小学校のAIリテラシーを育成し、中学校・高等学校それぞれの段階で上の、また上のリテラシーを育成することが大切だと考えている。
「国語教育と同じように、学年に合わせて学習を積み重ねて力をつけていけば、大量データをさまざまに扱うデータサイエンスにも結び付きます」。
※1 STREAM(Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics)
※2 Artificial Intelligence
※3 Information Technology

English performance festival
世界に向けた発信力を
川原田先生は「30年後に必要な力はなんだろう」と考えて、プログラミング学習、使える英語、コミュニケーション、そして探究の学びを進めてきた。
自身も毎日25分間のオンラインで海外の人と会話をして英語力を磨いている川原田先生は、高学年にフィリピンの英語講師と1対1で向き合うオンライン会話学習を実施した。残念ながらコロナ禍で中断しているが、インドネシアの姉妹校との交流は続いている。
「インドネシアの学校では6年生から準備して11年(高2)生になると研究発表を外部にも発信しています。また、10年生がユーチューブでライブ配信した発表会は、日本にいる私たちも鑑賞できました。それを見ると、小学部も外部への発信力の重要性を痛感します」。
2年生から「英語パフォーマンスフェスティバル」を開催し、全校コンテストは相模女子大学グリーンホールで行っている。プログラミングではいくつものロボット競技会に参加して入賞を果たしている。それに満足することなく、小学部が社会に向けて発信することを、川原田先生は考えている。
最近、川原田先生は、造形展の仕上げに夢中の子どもたちの教室へ入り、図工科主任の森玄太先生のリモート指示を受けてサポートする体験をした。
「ネットワークは自由度を高めることができます。英語が使えれば世界の人とつながることができ、世界にある多様な選択肢も見えてくる時代です」。
23年度に向けて、オーストラリア・ターム留学の準備を進めている。これは、3か月間をオーストラリアの小学校で留学生活を送るプログラムで、その地域の生活や文化を体験することを目的にしている。言葉が異なる人たちとコミュニケーションする力を養うためには、人と向き合う経験が大切だ。
高学年の希望者が対象となる見込みだが「4年生で実施できたら一層効果があがると思います。3か月を乗り切ったら、ずいぶんたくましくなって帰ってくるでしょう」。

探究発表会
探究の先にある行動力
小学部では「探究の時間」を、〈目指す子ども像「自分からできる子」〉にふさわしい学びと位置付けている。
高学年は週1.5時間、自分の研究テーマに向き合って調べ考える学習に取り組み、各学期の最後に設けられた1週間は、活動を振り返りながらみんなで意見交換をし、また成果をまとめて発表する。
4年生はクラス担任の指導で行われるが、5・6年生はゼミ形式になる。子どもたちは、自然や社会の事象等、興味・関心のある事柄から、研究テーマを決定する。
科学、スポーツ、芸術など12前後のゼミが開講され、10名前後の児童と教員で構成される。
「AIをはじめ、ますます科学技術が進歩していくうえ、新型コロナウイルスによるパンデミックのようなことも起こり、社会のあり方は変わってきています。これからも、予測を超えた困難にぶつかった時に、柔軟な発想で解決しようとする行動力が求められます。自分のやりたいことを明確にして、独自の工夫をしながら問題解決を図る探究の姿勢を、小学生のうちに育むことで、将来必要になった場合に発揮できる力になります」。
21年度、子どもたちは、大学の先生から「研究のしかた」という講義を受けた。
予め子どもたちが提出した「どうやって情報を集めればいいのか」「行き詰ったときはどうしたら…」などの質問に答を得る形で話が進み、子どもたちはときに大きくうなづきながら聴き入る。なかでも、先生からの「発表会は基本的に自分が探究したことを話す場です」「プレゼンテーションは自分も研究の仲間を集めるつもりでやりなさい」という言葉は子どもたちの心をとらえた。
「大学の先生によい影響を与えていただきました。個人の力を伸ばし、挑戦する行動力を引き出すことが探究学習のよさです」と、川原田先生は成果を感じている。

造形展

タブレットを使った授業
自由にものづくり
ジャンルは異なるが、自分でテーマを決め、プランを立て、一人で制作に没頭するのは図工科の自由制作も同じだ。
5・6年生は2学期の4か月間を使って立体と平面の作品を1点ずつ制作する。木工作でも紙工作でも陶芸でもよい。絵でも版画でもよい。使う道具や材料、制作方法などを自分で調べ、工夫し、自分の力で制作を進めていく。
「1年生から作品づくりをしてきた延長線上にあるからできる」と森先生は言う。
「低学年から少しずつ技法を学びながらだんだん自由度を大きくしていきます。同じ粘土を渡しても、めいっぱい大きくつくる子、小さくまとめて粘土を余らせる子といろいろですが、達成感を得ることもつくる目的の一つですから好きなようにすればよいと思っています」。
2月の造形展には、自分のつくりたいものをつくった、全校生の独創的な作品が並ぶ。
陶芸は1年生から毎年テーマを変えて制作する。6年生のテーマは「使う食器をつくる」が定番。使う場所と時間と人を想定し、さらに丈夫で洗いやすいなどの条件も満たす食器をつくる。その結果、「自分が20歳になった時に使う徳利とお猪口」とか、「家族の人数分のマグカップ」とかができ上がる。
「なぜ?、不思議だ!と思う好奇心、探究心は、自分の前に立ちはだかる課題へ果敢に挑戦する力に変わります。子どもたちの未来が大きく変わろうとしているこの時代に、小学部の教育も、よりよい教育へ向けて変化をしていくと思います。子どもたちが小学部で学んだ力を基に大きく羽ばたくことを願い、私たち教員は力を合わせて取り組んでいきます」。
先生たちの、子どもたちと一緒に面白がる心と探究力に、ますます期待が高まる。
School Data
| 設立年 | 1951年 |
|---|---|
| 学制 | 共学(男子2:女子3)※学年により変動あり |
| 姉妹校 | 相模女子大学大学院、相模女子大学、相模女子大学短期大学部、相模女子大学中学部・高等部、相模女子大学幼稚部(認定子ども園) |
| 児童数 | 1学年約80名(28名×3クラス) |
| 授業日・学期 | 週5日制・3学期制 |
| 転入・編入 | HPでご案内します |
| 昼食 | 給食(火・水・木は希望者給食) |
| 放課後支援 | 放課後クラブを敷地内に併設 |
| 初年度費用 | 1,050,400円(2021年度) |
| 進路 | 男子は外部中学校受験 |
| 学校説明会 | 5月12日(木)、6月12日(日)、7月28日(木)、9月2日(金)、9月18日(日) |
| オープンスクール | 7月24日(日) 詳細は学校HPをご覧ください。 |
※上記は2022年5月時点(冊子「スクールダイヤモンド2022年春号」)での情報です。
最新情報は各校のホームページ等でご確認ください。
http://www.www.sagami-wu.ac.jp/sho/
アーカイブ
- 学校Webサイト(五十音順)