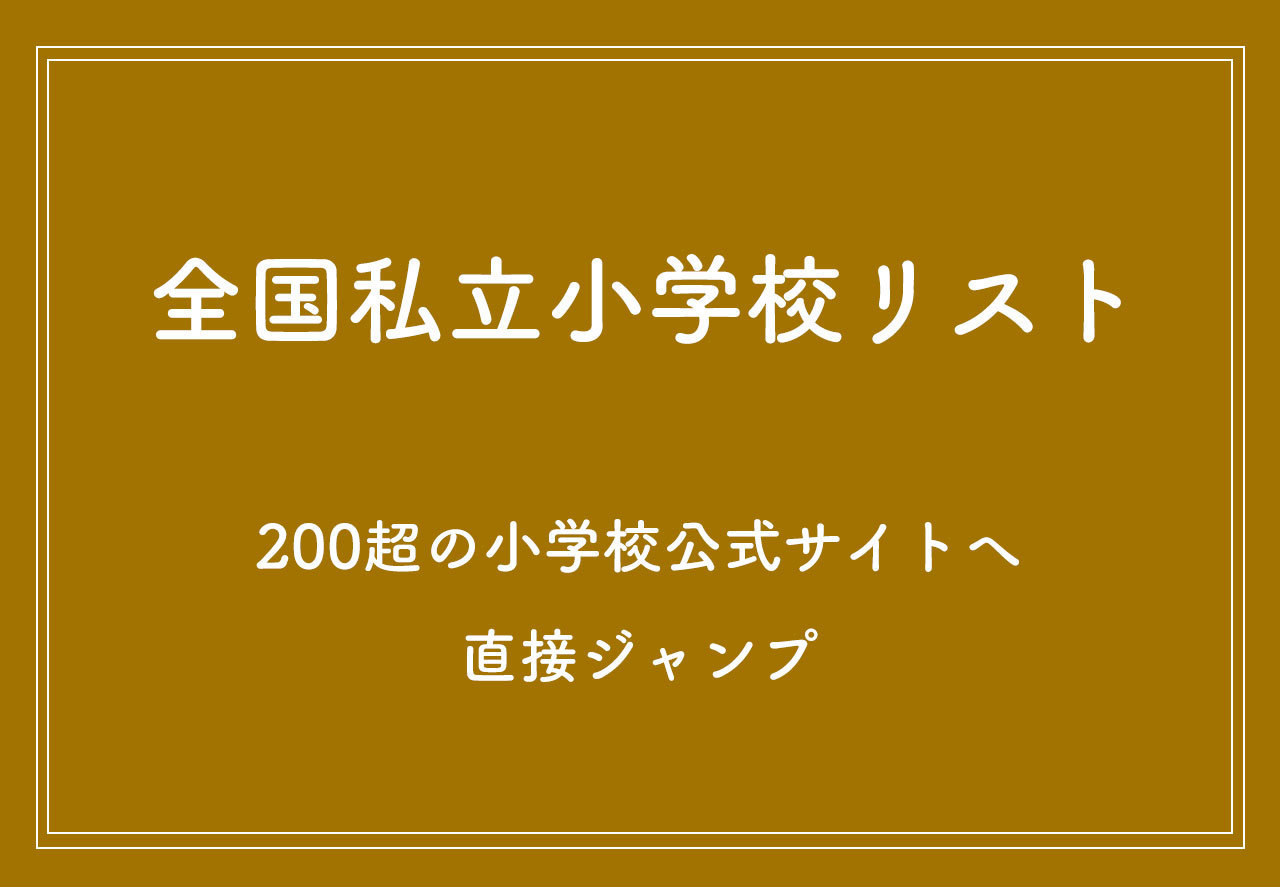東京都市大学付属小学校

教育目標
「高い学力の定着」と「豊かな心の育成」を柱に、
明るく楽しい学校づくり
〒157-0066 東京都世田谷区成城1-12-1
TEL:03-3417-0104 FAX:03-3417-1332
https://www.tcu-elementary.ed.jp/
最寄駅●成城学園前駅(小田急線)より徒歩10分
「食育」から広がる感性と探究心 さまざまな体験や行事で力をあわせ 「高い学力」「豊かな心」を育む6年間

食育の教壇に立つ福田順彦シェフ

食育プログラムで「イワシの手開き」に
挑戦する子どもたち
「イワシの手開き」で命を学ぶ
「うわっ、冷たい。ぬるぬるする!」教室に子どもたちの元気な歓声がはじける。4年生の児童が挑戦するのは「イワシの手開き」だ。この授業の先生は、セルリアンタワー東急ホテルの福田順彦総料理長。まず福田シェフが教室の前に立ってイワシを持ち、手でさばいていく。「指を背骨に沿わせて開いていきます。ほら、スッと開いたでしょう?」。きれいにさばかれた姿に「すごい!」と感嘆の声を上げる子どもたち。さっそく一人一尾のイワシを子どもたちも慎重に開き始める。はじめはおそるおそるだった手つきも、福田シェフから「指をゆっくり滑らせてみて」と声をかけられ、しだいに上手に開けるようになっていく。
次のステップは、塩とこしょうで軽く味つけしたイワシをフライパンで焼く作業だ。オリーブオイルを入れて予熱すること数十秒、いざ、イワシをのせると、フライパンからジュワッと音が立ちのぼる。「油がはねそうでこわい!」と身がまえる児童に、「ゆっくりやれば大丈夫だよ」と仲間が励ます光景も。焼き上がったイワシを口にすると「ちょっと苦いけど、いけるかも!」「しっぽまでサクサク!」と驚きや喜びがあふれる。普段魚が苦手という児童も、「自分で調理したから食べられた」と笑顔を見せる。
授業を終えた子どもたちからは「最初はこわかったけど、うまく手でさばくことができて楽しかった」「お母さんと一緒にスーパーで魚を選んで、家でも調理したい」などの声も。魚への興味がいっそう強くなったようだ。
「子どもたちは普段食べている魚の姿や形、大きさを知らないことが多く、命をいただいているという実感が希薄になりがちです。今回、イワシを手でさばくことによって、食材そのものへの感謝の気持ち、敬意を持ってほしいというねらいがあります」と食育担当の滝澤宣頼先生は話す。
五感で学ぶ「福田メソッド」
本校が誇る人気の体験学習「福田メソッド」は、食の本質を学ぶ、4年生対象の食育プログラムだ。「イワシの手開き」はその11回目にあたる。
年12回の授業では、まず味覚の基礎から学び始め、五感を研ぎ澄ませて温度や音による味の変化を体験する。次に子どもたち自身が種をまいて育てた野菜を収穫し、調理し、味わうことで、食材への関心を高める。また、豊洲市場見学では、福田シェフから魚や野菜の見極め方を学ぶフィールドワークもある。こうした一連のカリキュラムにより、子どもたちは味わったり匂いを感じたりする中で、食材への関心と深い洞察力を身につけていく。
このプログラムの成果は着実に表れている。「以前はおいしい、おいしくないという単純な表現で感想を言っていた児童が、『甘みが強すぎる』『辛すぎておいしくない』など、より具体的に味を表現できるようになりました。また、食事をさっと済ませるのではなく、ゆっくり味わって食べる習慣が身につき、家庭で料理に挑戦する子も増えています」と滝澤先生。
「食は生きていくうえで欠かせないもの。だからこそ、子どもたちには五感で味わい、背景にある文化、命の尊さを考える機会を持ってほしい。そうして毎日の食事がより楽しく、意味のあるものになればうれしいですね」と期待を込める。
二つの柱で育む確かな土台
「高い学力」と「豊かな心」の2つを柱として掲げる本校では、児童のほぼ全員が中学受験する。だが、教育の目標は合格することだけではない。2024年度に着任した岡野親校長は、公立高校などでの豊富な指導経験から、小学校教育の重要性をこう語る。
「学力はどんどん積み重ねていくものですが、小学校はいわば土台を築く時期。さらに人格形成においても小学校時代は極めて大切です。のちの学校生活や社会生活の基盤となる学力と同時に、人間性を育てる時期でもあるのです。だからこそ、『高い学力』と『豊かな心』の2つを大切にしているのです」

休み時間に体育館で思い思いに遊ぶ
体験と行事が育む「豊かな心」
この理念の実現のため、本校では体験学習と行事を豊富に取り入れている。冒頭で紹介した「福田メソッド」のほか、縦割り3色対抗での運動会や音楽発表会、異学年交流活動や季節を体感できる体験学習、競書会・大縄大会など活動は多岐にわたる。これらは単なるイベントではなく、子どもたちの協調性や思いやりといった「豊かな心」を育み、さらには挑戦する意欲や問題解決力を高める土台となっている。
宿泊行事も1年生から段階的に取り入れ、子どもたちの成長を促している。「1年生は4月に入学して7月には1泊2日、2年生からは2泊3日、4年生になると3泊4日と、学年が上がるにつれて宿泊行事を充実させています。これほど多様な体験の機会を早い段階から設けているのは、子どもたちに多くの『場数』を踏ませることが大切だと考えているからです」と岡野校長は説明する。
こうした体験の積み重ねによって、低学年では自己主張が強かった子どもも、6年生になるころには相手の話をしっかり聞き、建設的な対話ができるようになる。また、餅つき大会では、自分の番が終わった子どもが「つくときよりも抜く時のほうが力がいるよ」と次の子にアドバイスをするなど、日々の体験から学んだ協調性や思いやりが、自然と行動に表れるようになる。
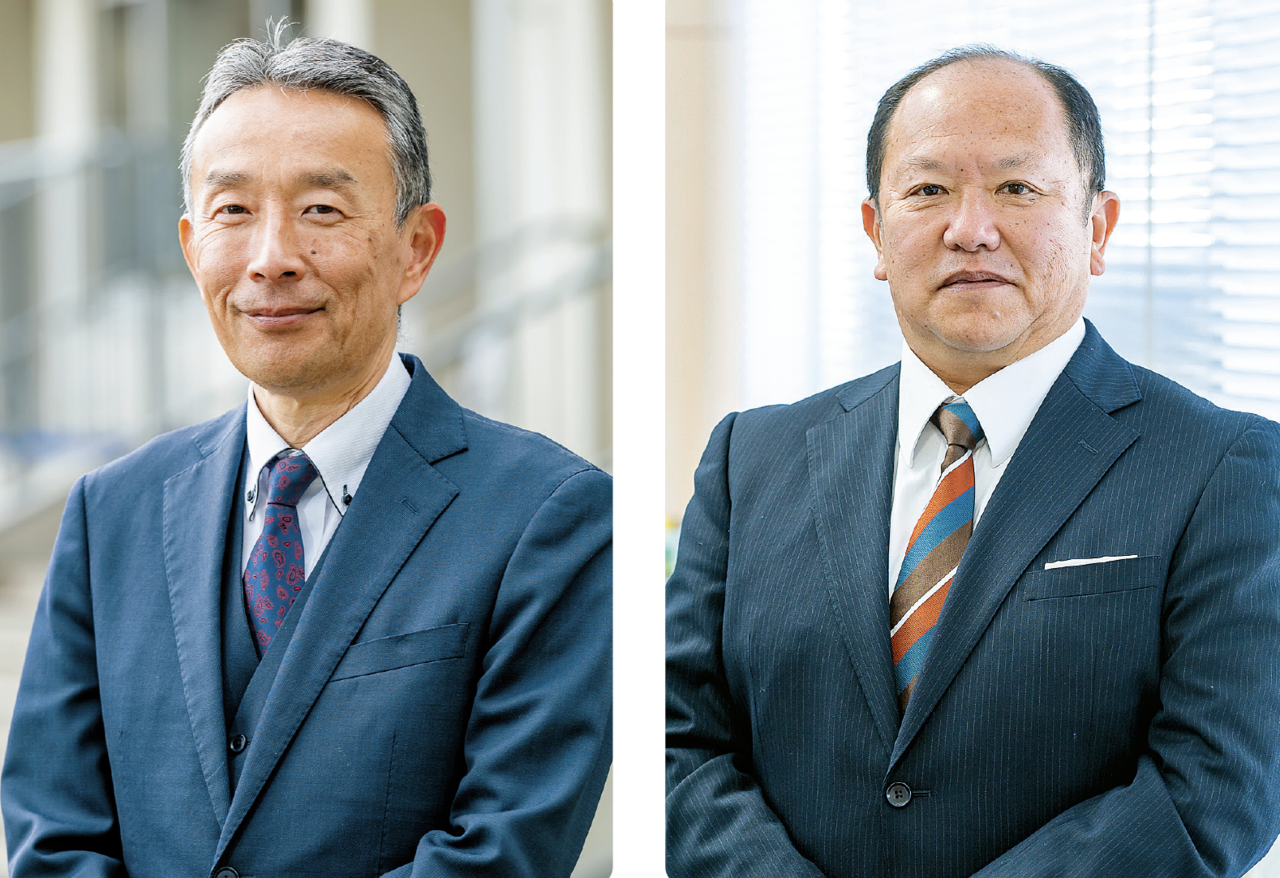
岡野親校長(左)と
食育担当の滝澤宣頼先生(右)
保護者の声をもとに改革を実行
岡野校長は、「『不易流行』という松尾芭蕉の言葉があるように、大切なのは、変わらない本校の伝統は守りつつ、新しい時代にふさわしい変化を遂げること」と語る。近年では、共働き家庭の増加や子どものメンタルヘルスへの関心の高まりといった社会変化に対応するため、アフタースクールの拡充や、スクールカウンセラーの導入にも積極的に取り組んでいる。
また、岡野校長の発案で、保護者に対するアンケートも実施。これまでも、『土曜授業のあり方』などについて意見を募ってきた。今後もきめ細やかな声をすくい上げ、反映させる学校運営をめざしている。
「保護者の声を直接聞くことで、学校と家庭の間に隠れていたニーズが見えてくることがあります。これからも、学校の方針を一方的に決めるのではなく、保護者の声に真摯に耳を傾け、ともに協力して子どもたちがいきいきと過ごせる学びの場をつくっていきたい。教員たちは、子どもたちをわが子のように慈しみ、日々惜しみない力で子どもたちの成長を後押ししています。これからも本校ならではのよさを維持しつつ、社会の変化に柔軟に対応できる教育環境を整え、子どもたち一人ひとりの未来への可能性を広げていきます」(岡野校長)
School Data
| 創立年 | 1956年 |
|---|---|
| 学制 | 共学(男女比1:1) |
| 系列校 | 学校法人五島育英会(東京都市大学、付属中学校・高等学校、等々力中学校・高等学校、二子幼稚園、塩尻高等学校) |
| 児童数 | 1学年76名(38名×2クラス) |
| 授業日 | 月~金、土(隔週) |
| 学期 | 2期制 |
| 昼食 | 給食/木曜はお弁当 |
| 放課後支援 | アフタースクール(最大18時まで預り可) 課外プログラム(サッカー、ランニング、プログラミング、英語、生け花) |
| 初年度費用 | 1,471,000円 |
| 進路 | 系列校進学34%(2025年3月) |
| 学校説明会・学校公開等 | いずれも要予約 詳細は学校HP |
※上記は2025年5月時点(冊子「スクールダイヤモンド2025」)での情報です。
最新情報は各校のホームページ等でご確認ください。
https://www.tcu-elementary.ed.jp
アーカイブ
- 学校Webサイト(五十音順)